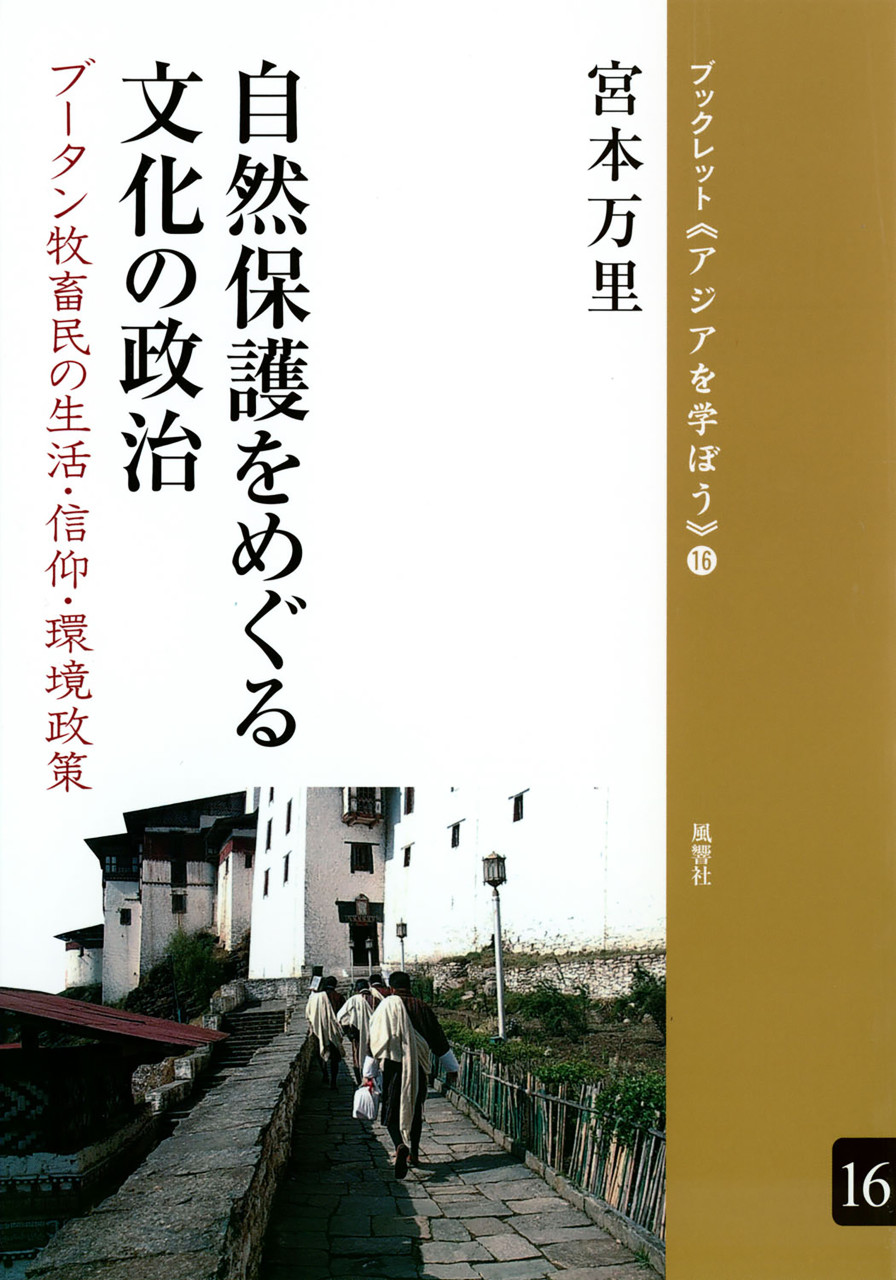
販売終了
作品説明
本書は、ブータン政府の環境主義はブータンの仏教思想や伝統的慣習に根付いてもともとあったとする見方や、「賢明で慈悲深い国王と政府」と「従順な国民」との関係からのみ単線的にブータン社会を理解するやり方に絡めとられることなく、ブータンの環境主義と農村社会の暮らしとを、具体的な政策の変遷や長期的なフィールド調査のデータから捉えなおしていこうとするものだ。そのために、本書は二部から構成される。まず第Ⅰ部では、政府の森林政策の変遷および環境政策における語り、国際社会へ向けた王族の声明文、仏教思想の位置づけ、グローバルな環境主義の潮流といった複数の要素に目を向けながら、現代ブータンにおける環境主義の系譜を辿っていくことにする。そして、第Ⅱ部では、政府の自然保護政策の下で抑圧されつつも、様々な生活実践や宗教実践をとおしてそれらの制度をとらえ返し、読み変え、交渉する村落住民のエイジェンシーを、国立公園下の村落で実施してきたフィールドワークの知見をもとに描き出してきたいと思う。(本文より抜粋)
【目次】
序論──「環境にやさしい我々」という自画像をめぐって
第1部 森林政策における「環境主義」の起源
一 開発導入期の森林開発(一九五〇年代~)
二 ディープエコロジーの思想潮流と仏教の接合(一九八七年~)
三 「伝統維持=環境保護」イデオロギーの形成(一九九〇年~)
四 グローバルな価値のなかで生きる(一九九二年~)
五 環境保護を制度化する(一九九五~)
六 まとめ
第2部 自然環境保護とはなにか──国立公園における環境政策と牧畜民
一 ブータンの国立公園
二 「森林」定義の変遷
三 畜牛保有と家畜飼育形態
四 自然環境保護への「脅威」としての森林放牧
五 森林放牧と牛の屠殺をめぐる文化の政治
六 まとめ
あとがき
シリーズ一覧
-
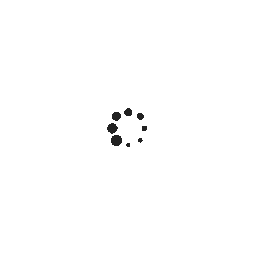
海を渡った騎馬文化 馬具からみた古代東北アジア
考古学一般 -
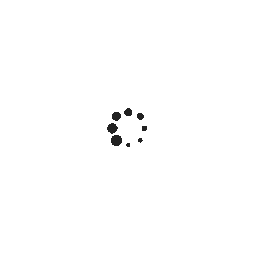
-
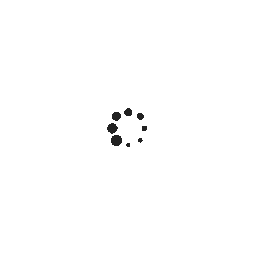
-
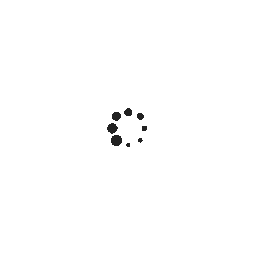
-
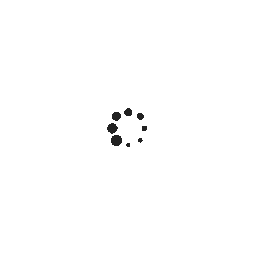
-
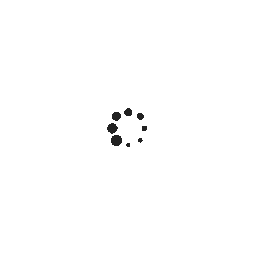
-
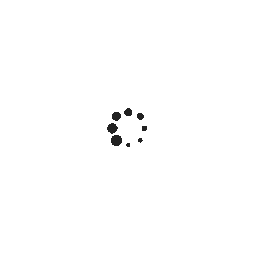
-
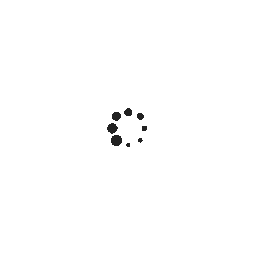
-
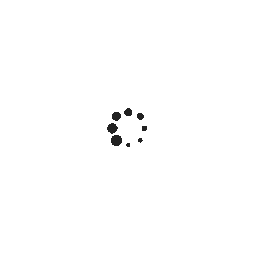
-
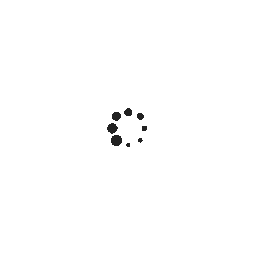
チベット人の民族意識と仏教 その歴史と現在
宗教/仏教
